 |
今朝はあいにくのうす曇の天気で、肌寒い中、歴史の街、佐倉を訪れました。今は、東京に通勤するサラリーマンのベットタウンとなりましたが、江戸時代に重責をなした旧佐倉藩の城下町として栄えてきた歴史ある街です。
点在する名所旧跡を訪ね歩くには一日では回りきれません。寝坊したことでもあり、今日は、一回目、佐倉城址公園周辺を歩くことにしました。
京成佐倉駅を降り立って、まず、駅前の佐倉観光協会を訪ねました。ここには、佐倉周辺のガイドマップなどパンフレット類が豊富で便利です。
駅前の成田街道につながる大通りを西へ向かいました。 |
| 成田街道に入ると一段と車の通行量が増えます。歩道が狭く少し歩きにくく感じました。 |
 |
 |
成田街道に面して、ここが国立歴史民俗博物館の入り口です。ここは、7〜8年前に家族連れで見学に来たことがあります。
|
入り口に向かう道すがら、この石仏が目に留まりました。大分県にある大日如来像で、保存修理されて元の場所に復元されたそうです。これは、その複製のようです。
|
 |
 |
ここが国立歴史民俗博物館の入り口です。
大変大きな博物館で、半日掛りで見学した記憶があります。 |
佐倉城址公園の馬出し空濠跡です。この堤の向こうに深い濠が掘られています。
|
 |
 |
石垣に根付いたケヤキの木です。相当な樹齢と思われます。 |
博物館の裏側から全景を見ています。
|
 |
 |
こちらも立派な桜の木です。桜の季節にまた来てみたいと思います。
|
公園内は大変よく整備されていて塵一つ落ちていません。
近隣の年配の夫婦連れの散歩する姿を沢山、見掛けました。 |
 |
 |
公園の片隅にはこんな茶室が設営されています。
|
落ち葉の敷き詰める林の空気を一杯、吸い込みました。
|
 |
 |
公園を出ると銀杏並木が美しく色づいていました。
ちょうど見頃のようです。 |
麻賀多神社に向かう途中、道端にこの史跡を見掛けました。
佐倉城は、もともと石垣ではなく土塁をめぐらした自然の地の利を生かした造りになっていたそうです。
広大な敷地に幾重もの土塁が重なり、房総随一の規模と堅固を誇ったといわれています。
この大手門に始まり、立派な三層の天守閣もあったそうですが、それらは全て明治の軍制によって解体されてしまいました。
残念なことです。
|
 |
 |
ここは麻賀多神社の入り口です。中では七五三のお参りの家族が大勢詰め掛けていました。
今回は遠慮して参拝はパスしました。
|
これは麻賀多神社前にある佐倉養生所の史跡です。江戸藩主堀田正睦(まさよし)に招かれた蘭医佐藤泰然(たいぜん)がここに西洋式病院を開いたそうです。
ここから東に行くと、佐倉順天堂記念館があり、これは泰然が開いた近代医学の発展に大いに寄与したわが国初の私立病院です。次回、足を運ぶ予定です。
、 |
 |
 |
佐倉市立美術館に着きました。
入り口には、こんなモニュメントが展示されています。 |
これは確か浅井忠の銅像です。
|
 |
 |
こちらがモニュメントの正面でした。
「風景」という題名が記されていました。 |
| この佐倉市立美術館は、もともとは大正時代に川崎銀行佐倉支店として建てられた建物だったそうです。ネオ・ルネッサンス様式という建築様式を取り入れているそうで、今でもむしろモダンに感じました。 |
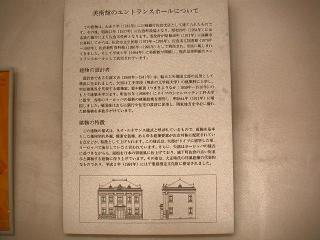 |
 |
入り口から入ったエントランスの天井を仰ぎ見るとこのモニュメントが空中に浮かんで見えます。
ここで、一息入れて駅へ戻りました。
次回は、佐倉の東側を歩く予定です。
おしまい。
 |