 |
今日は連休最終日の11月4日、昨日までの天気からはうって変わって、朝から晴天に恵まれました。
総武線市川駅は、9時を過ぎた時間帯にお出かけの人出で混雑していました。
市川は、古くから東京のベットタウンとして発展してきたイメージがありますが、ここは、古墳や国分寺もある歴史の街でもあります。見所が数多くあるので、2,3回に分けて訪れることにしました。一回目の今日は、文学の道から、弘法寺を訪ねることにしました。 |
駅前から千葉街道に出て、駅舎を振り返りました。
空は雲ひとつない快晴です。 |
 |
 |
千葉街道を東京方向に見ています。
|
| 千葉街道沿いにこんな海産物を売る古風なお店があります。 |
 |
 |
駅前十字路から市川真間駅方向に少し行くと、真間銀座通りに出会います。
|
真間銀座通りを京成線方向に歩いてみました。
石畳の歩道が整備されてお洒落な商店も見掛けます。
|
 |
 |
市川駅からは、こんな風な甘味屋さんをよく見掛けます。
|
千葉の県産酒を売る酒屋さんです。
|
 |
 |
真間銀座通りから京成真間駅を過ぎてホームを振り返りました。
|
市川文学の道に入る手前に、相田みつをギャラリーが開いていました。
|
 |
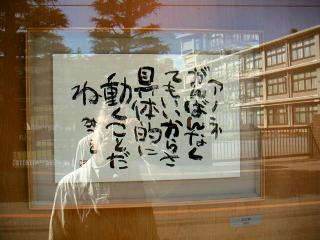 |
なるほど、そうですね。
私のこの「のんびり散策記」も10回目となりましたが、この気持ちで続けるつもりです。
|
市川は明治からの文豪ゆかりの地でもあり、真間史蹟保存会によって、このような記念の立板が作られて「文学の道」と名づけられた桜土手公園沿いの道に数多く立てられています。
これは、この地に江口章子と同棲して住んでいた北原白秋です。
|
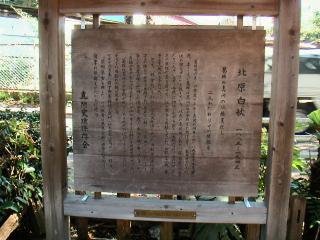 |
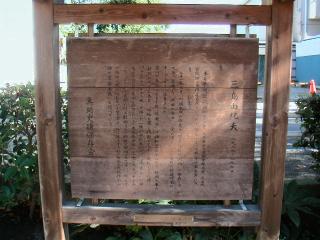 |
こちらは三島由紀夫です。このあたりをよく散策したそうです。
|
| 住宅街に沿って歩道が整備されていて、幼児の遊び道具になるモニュメントが沢山おかれています。 |
 |
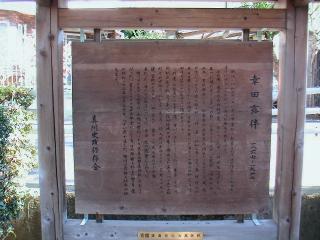 |
幸田露伴は東京向島に住んでいたそうですが、このあたりのことがよく書かれているそうです。
|
| 市川文学の道、創設の記念碑です。 |
 |
 |
文学の道を突き当たると真間川に出ます。
|
中野孝次は市川に育った小説家です。
|
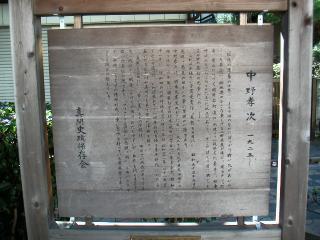 |
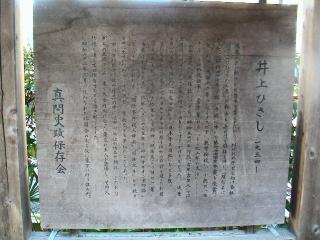 |
井上ひさしは、市川の北国分に住んでいたそうです。
|
手児奈橋に向かう途中に見掛けた小さなお堂です。
とてもよく手入れされていました。
|
 |
 |
宋左近の絵文です。
|
| 手児奈橋に出ました。 |
 |
 |
手児奈橋から真間川を船橋方向に見ています。
|
ここが手児奈霊堂の中庭です。
その昔、超美人の手児奈姫はあまりのプロポーズの多さにわが身の置き所なく、池に身を投げたという謂れもあるそうで、このお堂はどことなく優しげな趣がありました。
お堂の前では七五三の記念写真の真っ最中でした。
|
 |
 |
お堂の中では、ちょっと変わった読経のリズムが聞こえてました。再現できないのが、残念です。
|
| お堂の前の歩道は、桜吹雪をあしらったアスファルトです。 |
 |
 |
弘法寺に着きました。
この石段の上に本堂があります。
|
弘法寺は、行基が手児奈姫を供養して建立したと言われています。宗派が変わり、現在は、日蓮宗に改宗したそうです。
石段の上から、入り口の参道を見下ろしました。
|
 |
 |
石段を登ると、この仁王門が迎えてくれます。
境内は大変静かで、小さな女の子と連れ立った親子の後に続いて入りました。
|
仁王門をくぐるとこの大きな本堂が目に付きます。
弘法寺は、明治二十一年に火災に遭い、灰燼に帰したそうです。この本堂は、近年になって、鉄筋コンクリート造りに立て替えられたものです。
|
 |
 |
境内には立派な古木が何本か、生き残ったようです。
|
| この木は、「伏姫桜」という立派な桜の木です。横に長く幹が伸びていて、支えなくしては立っていられない姿見です。 |
 |
 |
後ろに下がって全景を捕らえました。
花の咲くころにまた、見に来てみたいですね。
|
| 万葉の俳句が浮かんだら、このポストへ入れてください、とかかれてあります。 |
 |
 |
この大木の傍で、太極拳を楽しむおばさんを見かけました。
|
弘法寺をあとに、参道を下る途中、こんな古びた農家のような木造家屋を見かけました。
|
 |
 |
これが万葉集にも詠われているという「真間の継橋」です。
お昼前のこの時間になると、参拝に上ってくる人たちとすれ違いました。若い娘さん二人連れが多いのが意外でした。
|
京成国府台駅から帰路に着きました。
次回は、里見公園を訪れる予定です。
つづく。
 |
 |