 |
今日は朝からあいにくの曇り空。京成中山駅には、8時前に着きましたが、日曜日のやや早い時間なので、人影はまばらでした。
”中山”と聞くと競馬場を思い浮かべる人が多いかと思いますが、ここは日蓮宗の大本山、法華経寺の門前町として発展してきた町です。
京成中山駅を降りて駅を振り返り、スナップしました。
左側の御餅屋さんの壁の「だいふく」にまずは、ひとなごみしました。
|
駅からは法華経寺まで200m足らずですが、石畳が敷かれ歩きやすくなっています。
時間が早いとはいえ、日曜日の人出はほとんどありません。成田山のような観光地の趣は感じませんでした。 |
 |
 |
法華経寺の入り口は、この黒門です。いかにも古びたいかめしい造りです。 |
寺院と隣り合わせでお饅頭屋さんが並んでいます。
ここは、「蜂蜜饅頭」が名物とのこと、残念ながらお店はまだ開いていませんでした。
当てにしていたのですが・・・・。
|
 |
 |
黒門を過ぎると、仁王門が見えます。別名、赤門とも呼ばれるそうですが、赤の朱塗りは、所々、その名残を留めています。仰ぐと光悦の筆による額があります。
|
仁王門の入り口の案内板です。
小奇麗ですが、分かりづらいので、地図が合った方が良いのですが、自宅に置き忘れたので、今回はこの看板をしげしげと眺め、頭に入れて中に入りました。 |
 |
 |
仁王門の両側には、阿弥陀仁王が門番のように立ちすくんでいます。 |
仁王門を過ぎると、両側にこんな小振りの寺院が立ち並んでいます。まるで、寺院の住宅街の趣です。
どうしてこんな風な様相になったか、よく分かりません。
これは、なかでも新築風の本光寺という寺院です。
|
 |
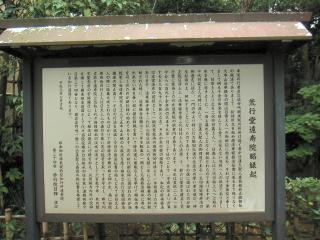 |
こちらは、本妙寺の入り口にある遠寿院の縁起を記した立看板です。どうも難しくて、よく分かりませんでした。
|
ちょっと中を拝見してみようかと、階段を上りかけたら、いきなり、この立て札が目に入りました。
最初、なんのことかよく分かりませんでしたが、よく考えると何か「不幸」があったのかな、感じていました。
調べてみると、やはり住職が亡くなられたりした時に、この立て札を立てるそうです。 |
 |
 |
仁王門の中の参道はこんな感じの石畳が続きます。
両側に建ち並ぶ寺院の入り口が見えます。
|
しばらく歩くと、商店が並んでいます。
どこもまだ、開店前のようです。
|
 |
 |
どういうわけか、野良猫を沢山、見かけました。
|
| 境内には大きな大木が何本か聳えています。 |
 |
 |
大変、分かりやすい絵地図です。
|
こちらも、樹齢何年でしょうか、しっかりと地面に立っています。楡の木ではないかと思います。
|
 |
 |
根元はこんな風に、まるで地面を咥えているようです。
|
こちらは境内右手にある絵馬堂です。
新しい絵馬は見当たりませんでした。
|
 |
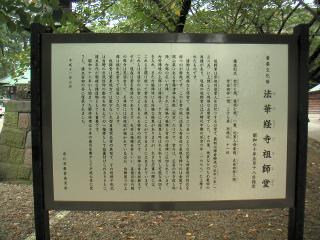 |
こちらは、宗祖日蓮聖人をお祀りする祖師堂の案内板です。何度も建て替えられて、現在の姿は、平成9年に完成したそうです。
|
ここは、石塔はあまり多くはありません。
危険防止の札も見かけませんでした。
|
 |
 |
祖師堂の前に、こんな小さな日蓮聖人の御仏姿が拝めます。
随分、朝早くからお世話している人達がいるようです。
身体を磨く手拭も洗濯して乾かしてあります。日常生活に溶け込んでいる仏さんです。
|
祖師堂にはお参りする人達が絶えません。
短パン姿で、ジョギングついでに手を合わせてゆくおじさんも見かけました。
|
 |
 |
祖師堂の裏側はこんな風な造りです。国の重要文化財に指定されていて、建物は大きな7間堂で屋根を二つ並べたような比翼入母屋造りが特徴だそうです。この建築様式で建てられている寺院は珍しく、他には岡山県にある吉備津神社本殿(国宝)だけだそうです。 |
祖師堂の裏手には、宗祖日蓮が日照りで苦しんでいる農民のために雨乞いをし、奇跡を生んだという伝説のある龍王池があります。
|
 |
 |
龍王池は、残念ながら、改修されて全く昔の面影はありません。
|
仁王門から入ると正面に経つ五重塔に向かいました。
元和8年(1622)に、本阿弥光室が加賀藩主前田利光の援助を受けて建てたもので、総高31.6m、江戸時代初期の様式では、千葉県唯一の五重塔だそうです。
|
 |
 |
五重塔の真下にこんな看板があり、この下の石は、国歌「君が代」に出てくる”さざれ石”のいわれとなった石で、大変、目出度い石だという意味のことが書かれています。
もともとは、岐阜県揖斐郡春日村にあったものだそうで、文部省の中庭を経て、ここに運ばれたものだそうです。
|
これがその石です。
確かに、苔がむしているようですが・・・・。
|
 |
 |
享保4年(1719)日禅上人の代に作られた大仏です。
大仏といえば、千葉県では鎌ヶ谷大仏が有名ですが、こちらはそれより、52年古いそうです。
|
大仏の側にあったこの信号機みたいなもの、さっぱり意味が分かりませんでした。
ひょっとしたら、初詣の混雑の時とかに使うのかな。
|
 |
 |
大仏裏手のこの柵で周りを囲ったこの不思議な砂場も、よく分かりませんでした。
案内板も見当たりませんでした。
時間の都合もあり、このあと、本院境内を通り抜けて、一路、奥の院に向かいました。
|
奥の院は、本院から徒歩、5分くらいの距離にあります。中山法華経寺は、日蓮聖人を保護し、帰依した千葉氏に帰属する若宮の領主富木常忍(ときじょうにん)と、中山の領主大田乗明(おおたじょうみょう)の子日高(にちこう)とが、共に館の内部に堂を建て、それぞれ寺院として法華経寺、本妙寺と称したのですが、のちに合体して一つの寺となり、法華経寺と号するようになったものです。富木常忍は、日蓮聖人の入滅後出家して日常(にちじょう)と号し、法華経寺はこの日常上人を開山にしているのですが、その日常上人の館の跡地がこの奥の院です。
|
 |
 |
入り口はこんな風に鬱蒼とした雰囲気です。
|
千体仏のお地蔵さんです。
お花が添えられています。
|
 |
 |
ここが若宮殿本堂です。
参拝者もほとんど見かけませんでしたが、手入れは行き届いていて、生活の臭いをふんだんに感じました。
ここを出て、若宮の住宅地を抜けて、中山競馬場に向かいました。 |
中山競馬場の厩舎沿いに歩くと、15分位で競馬場南門に出ます。
この日は、レースの日で、こちらは沢山の人出で賑わっていました。 |
 |
 |
ここから行田公園へ向かう道筋は、競馬場に向かう人とひっきりなしにすれ違いました。
幸い、顔見知りの人はいませんでした。
|
競馬場南門からレース場にそって少し歩くと、この熊野神社がひっそりと建っています。縁起を読むと、不審火に遭い、建て替えられたと書いてありました。
このお宮さんは、船橋大神宮の支社になります。
昔は、この地も浜辺だったそうです。
|
 |
 |
行田公園には、南公園を経由して入りました。
中は、広大な敷地で、こんな大きな歩道橋もかかっています。 |
歩道橋の下のスペースを使って、フリーマーケットを楽しむ人達を見かけました。
|
 |
 |
歩道橋から、西船橋方向を眺めています。
|
歩道橋から東方向、塚田の方角へ歩いています。ここまででおよそ5Kmの道のりです。
|
 |
 |
大きな芝生の広場があります。ここは、昔、息子のサッカーの試合に訪れたことがあり、その時の光景が蘇りました。
ここで、ベンチで一息入れました。
|
公園には、こんな小奇麗な林もあります。
|
 |
 |
行田公園を出て、少し道を間違え、遠回りしましたが、9:50 東武塚田駅から帰路に着きました。
おしまい。
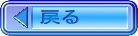 |